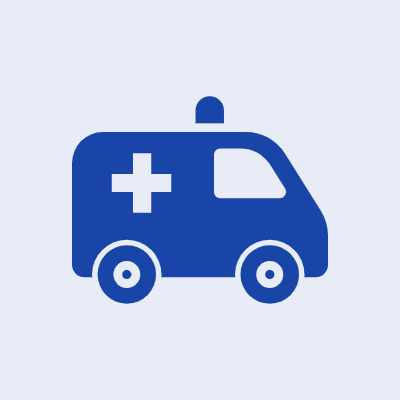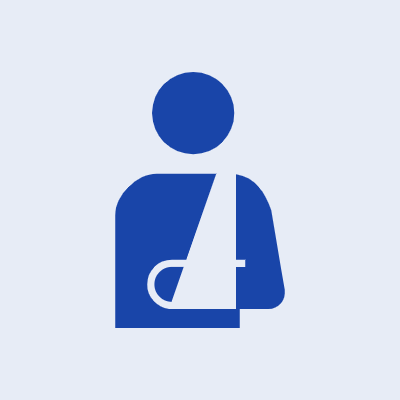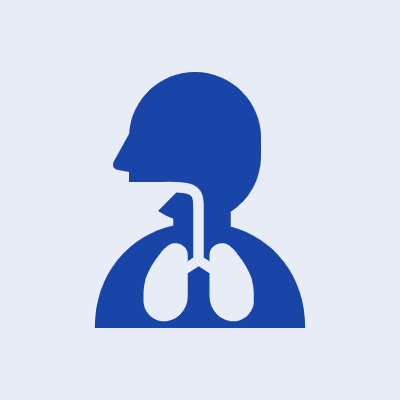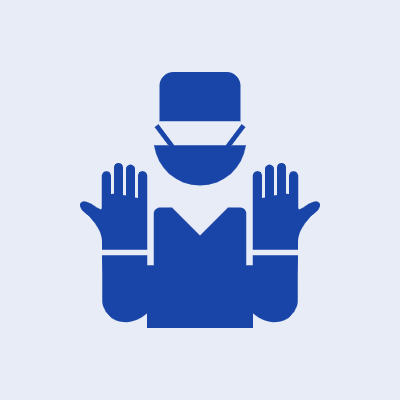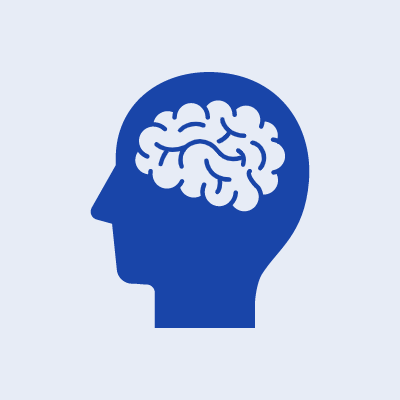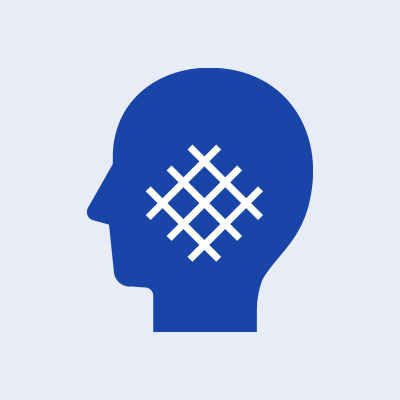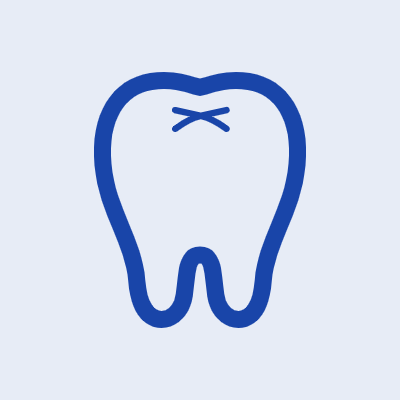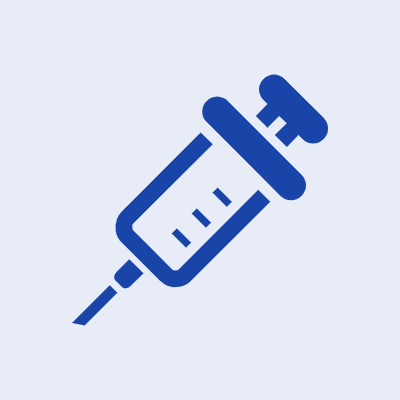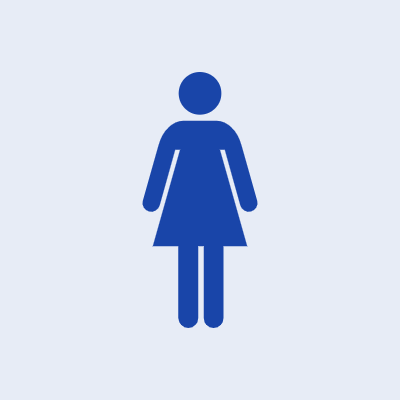身体拘束最小化のための指針
1.基本方針
身体拘束とは患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解するとともに、身体拘束を最小化する体制を整備し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない医療・看護に努める。
2.定義
1)身体拘束とは、患者の医療上の安全確保と保護を目的に、専用の道具を用いて、患者の体幹・四肢をベッドなどに固定し、その運動を制限する行為のこと。
2)身体抑制とは、患者の身体に直接、専用の道具を用いて固定し、運動を制限する行為のこと。
3.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
当院では身体拘束の中に、身体抑制を含むこととする。患者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合の身体拘束は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要素を満たした場合であり、可能な限り実施しないための努力をする必要がある。
1) 身体拘束の三原則
(1) 切迫性:行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い(意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮)
(2)非代替性:行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)
(3)一時性:行動制限は一時的であること
2)身体拘束の具体例
(1) 自己では着脱困難な介護衣(つなぎ服)の着用
(2) 手指抑制のための手袋(ミトン)の使用
(3) 上下肢抑制のための固定または体幹抑制のための固定
(4) 車椅子に座っている際の固定ベルトの使用
(5) ベッド柵4点固定(もしくは片側を壁付け、反対側を2点柵)
4.身体拘束の対象としない具体的な行為
当院では、入院患者を転倒転落や離院などのリスクから守るための対策として下記方法は身体拘束の対象としない。
・離床センサー(マットセンサー、転倒むし、ミッテル、サイドコール、タッチセンサー)
・患者からの希望による4点柵(ベッドからの転落に対する不安)
※てんかんモニタリング及びてんかん手術については発作時の安全対策として身体抑制説明・同意書を取得する。
5.日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を感じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
(1)患者主体の行動、尊厳を尊重する
(2)言葉や応対などで患者の精神的な自由を妨げない
(3)患者の思いを汲み取り、患者の意向に沿った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める
(4)身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
(5)薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する
6.身体拘束最小化のための体制
1) 身体拘束最小化チームの設置
身体拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員等から構成されるチームを設置し、以下のことを検討する。
(1)身体拘束に関するマニュアル等を周知するとともに活用状況を確認し、定期的な見直しを行う
(2)発生した身体拘束の状況や開始までの流れ、方法について、適正に行われているかの確認をする
(3)職員向け研修の企画・立案・実施
(4)日常的ケアを見直し、入院患者に対して尊重されたケアが行われているかを検討する
2) 身体拘束最小化のための職員研修
医療・ケアに携わる職員に対し、身体拘束最小化についての研修を年1回以上実施する。
3) 身体拘束を行う場合の対応手順
(1) 実施の可能性のアセスメント
身体抑制適正化対応フロー(資料1)を用いて患者の生命又は身体の危険性を評価する
(2) 医師の指示
身体拘束の可能性が高い患者に対して、指示を出す
(3) 説明と同意
医師より患者・家族へ身体抑制説明・同意書(資料2)を用い説明を行い同意を得る
(4) 危険行動防止策
危険行動防止策アセスメント表(資料3)を用い、危険行動予防を行う
(5) 身体拘束実施
危険行動防止策に効果が得られず、やむを得ない場合に身体拘束を実施する
(6) 二次的な身体障害予防
身体拘束中に予測される有害事象を観察し、対応する。観察したことは各勤務帯で記録や経過表に入力する
(7) 身体拘束解除にむけた検討
①身体拘束を行った場合、身体抑制解除への取り組みシート(資料4)を作成し、1日1回、患者の状態や介助に向けて取り組んでいること、身体拘束の方法や継続・解除等について検討し、記録する
②身体拘束の必要がなくなり次第、迅速に解除する
7.鎮静を目的とした薬物の適正使用について
1)不眠やせん妄の薬剤指示については、医師・看護師、必要時には薬剤師と協議し対応する。
2)行動を落ち着かせるために向精神薬を使用する場合は、患者に不利益が生じない量を使用する。
3)生命維持装置装着中や検査等で、薬物により鎮静を行う場合は、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えない適正な量を使用する。
8.この指針の閲覧について
当院の身体拘束最小化に関する指針は、患者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧できるように、当院のホームページに公表する。
令和6年5月策定
令和7年11月改訂